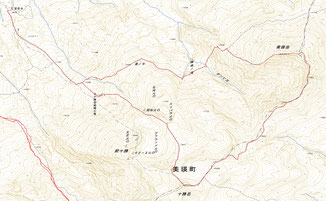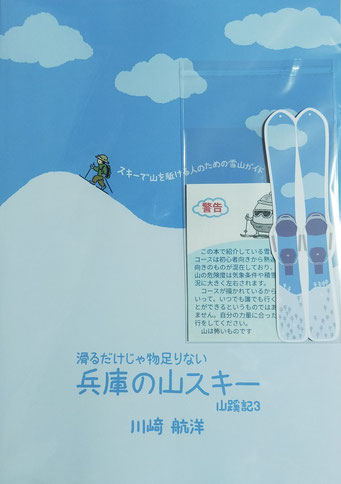南富良野の社満射岳。林道の除雪終点まで車で行って、そこから入山。後続バーティに抜かれて後を追うことになったが、素晴しい天気で急ぐ気にならない。タケノコ山から社満射岳を往復して、タケノコ山に戻り、そこで初めてシールをとる。タケノコ山へはボーダーやスキーヤーが沢山入っているらしい。できるだけ荒らされてない斜面をとったつもりが一谷間違えた。ルートの修正をしながら気ままに下る。どこでも歩き滑られるのがテレマークの楽しさかも。
北海道
北海道の山旅
北海道の山は雪線が低く、標高1000㍍でも本州の2000㍍級の雰囲気がある。
白い山々が魅力である。
ここでは72座登っているが、
そのうちの57座はテレマークスキーを履いてのスキー登山になる。 (2024年7月現在)
〇札幌時計台〇函館山〇すすきの・狸小路〇ニシン御殿〇襟裳岬〇宗谷岬〇藻岩山〇神威岬〇富良野
●札幌ラーメン●旭川ラーメン●豚丼●ジンギスカン●ウニ●トキシラズ●シシャモ●ホタテ●ニシン●シマエビ
●バタジャガ●サッポロビール
〇登別温泉〇丸駒温泉〇豊浦温泉〇ルスツ温泉〇川上温泉〇北湯沢温泉〇むろらん温泉〇伊達温泉〇駒ノ峯温泉
〇東大沼温泉〇朝里川温泉〇豊平峡温泉〇キロロ温泉〇小金湯温泉〇岩内温泉〇五色温泉〇雪秩父温泉〇吹上温泉
〇ニセコワイス温泉〇ふるびら温泉〇岬の湯しゃこたん〇層雲峡温泉〇旭岳温泉〇愛山渓温泉〇くったり温泉
〇利尻富士温泉〇新見温泉(廃)
利尻山(1721M) 2014.7.14 2019.4.29~30
利尻山は雲の中だったが、正午ごろからは晴れるとの予報を信じて沓形から登った。途中で一瞬、麓の町や海が見えたものの、それ以後はずっとガスの中。予報は悪く外れて三眺山辺りからはすっかり雨になってしまう。「親不知子不知」やガレ場のトラバースなど問題なくこなして、鴛泊コースに合流した。ザレた登山道をわずかに登って着いた山頂は風雨で寒く長居はできなかった。もちろん景色なんぞはという状態で、利尻山の印象が「白い」の一言になってしまったのが残念。鴛泊へと下ったが、このコースも長く、次に来るならスキーの使えるときにしようと思った。
朝一番のフェリーで利尻島へ。鴛泊コースの遅い出発となったので、頂上までは無理だろうと思いながら登る。甘露泉の上あたりでスキーをはき、夏道がある尾根の西側の谷をつめていった。 長官山まで4時間半ほどかかり、ここで山頂をあきらめる。滑降は、その先の枝尾根から沢源頭の急斜面を選んだ。雪は日照で緩み、滑落しても大丈夫な状態。思い思いに滑って、晴天微風の1日を過ごす。
翌日はTさんとⅯさんが山頂を目指して早立ちし、残りのへたれ組は山麓彷徨と決め込んだ。もう1本西の沢へ入ろうとしたものの笹薮帯に遮られて断念。今年はいつもの年の半分の積雪量とか。引き返し、雪のつながる尾根を台地あたりまで登ってみた。帰りは昨日同様の楽しい滑降。 夕方には、T・Mパーティも帰ってきて北野営場でのテントの中で、打ち上げとなった。
大雪山(旭岳:2291m) 2013.7.2 2019.4.30
2013年
旭岳ロープウェイは10分間で標高1600mの姿見駅まで運んでくれる。そこから山頂までは標高差700m弱の登りだから、ちょうど半分くらいの位置から登ることになる。有名な山だから登山者は多い。下山に天人原を通って歩いたのは、往復のロープウェイ代を惜しんだからではない。
2019年
朝一番の大雪山旭岳ロープウェイにメンバー6人とともに乗る。姿見駅を下りてから右手の尾根を2時間少々の登高で旭岳頂上へ。山頂にはもう多くの人がたむろしていた。
山頂から少し尾根を行き、折り返すようにして旭岳北の大斜面を滑降。途中、コケモモの絨毯の上でワインを開け、令和元年、最初の滑降を祝う。姿見駅までは山腹の長いトラバースだが、スキーはよく走った。あとはゲレンデに入り、スノークルージングを楽しむ。ロープウェイを用いての上だが、登り労力が少ないのに滑降距離が長いというコストパフォーマンスの良いコースだった。
黒岳(1984m) 2016.5.9
朝一番の黒岳ロープウェイを待って出発。101人乗りのゴンドラは、私たち夫婦2人きりで貸し切りだった。リフト運休中の 黒岳スキー場を歩いて登る。リフト終点からは急登が頂上まで続く。右手の尾根筋から、左の斜面へと大きくジグを切ながら登りついた黒岳頂上は、昨日の暑寒別岳同様の烈風。カムイミンタラの周遊はあきらめて早々に退散することにした。
下りの急斜面は斜滑降にキックターン。雪は適度に柔らかく、私は滑りたかったのだが、女房が怖がるので山ヤの原点に立ち返り安全優先で下りた。滑落の心配のない場所から滑降に切り替えスキー場へと滑り込んだ。
山頂駅で振り返ると、私たちのみっともないジグザグシュプールが広大な斜面に刻み込まれているではないか。
安足間岳(2194m) 2016.5.10
愛山渓温泉への19㌔の道が9日に開通したので、大雪山行きを変更して、その北にある安足間岳という余り名の知られていない山に転進した。一カ所谷を渡る所でモタモタしてしまった。そのせいでもないが、今シーズン1番乗りのつもりが、後続のご夫婦に抜かれて2番乗り。
安足間岳直下のカールを思わせる谷間の斜面、本州でもなかなか見ることのできない広大な景観。登りの時にはクラストしていた雪面も下る頃にはすっかりゆるんでいて、沼平の広い雪原とともに、すばらしい滑降が楽しめた。
暑寒別岳(1492m) 2016.5.8
北大山岳部の歌に「暑寒の尾根に芦別に 北の山のザラメの尾根を飛ばそうよ」というフレーズがあり、暑寒別岳の名はずいぶん前から知っていた。この山を登りに行った。
新日本海フェリーで午後9時に小樽に着き、そこから登山口の暑寒荘まで150kmを車で走り、そこで車中泊した。翌朝、駐車場から出発し、長い長い尾根を登る。曇りから晴れに変わっていく天気が励ましてくれ、休み休みながら距離をかせいだ。ここは視界がきけばいいけど、ガスのときの下りは危ない尾根になることだろう。この日の難は風だった。頂上手前の大斜面辺りから、身体が浮くほどの強風に煽られ、少し怖い目をする。先行パーティは登頂をあきらめたのか、早々に引き返してくる。私たちはスキーアイゼンで踏ん張り頂上へ。
しかし、強風の中では居づらく早々に引き上げ、クラストした急斜面はスキーアイゼンをつけたまま下った。 雪面がややゆるんだ場所で、シールとアイゼンをとって滑降に移る。滑るにつれて調子にのり思い切り「ザラメの尾根を飛ば」したのである。
行きとはコースをかえて下った谷間では、陽光とせせらぎが出迎えてくれた。「雪消の沢の歌たのし」北大山岳部の歌の後半を思わず口ずさんでいた。
北嶺山(671m) 2022.1.20
旭川市北のぴっぷスキー場はスキー授業の小中高生と自衛隊の隊員でいっぱい。でも、広いので混み合う感じではない。気持ちよく何本か滑ってから、北嶺山へと歩いた。 林道には自衛隊の演習のトレースがあったが、それも途中で途絶えたあと、わずかにラッセルして頂上に立った。風も雲もない。 空の色が違うような気がする。眼下の白い平野、そびえる白い峰々。この風景に出会えただけでも来た甲斐がある。 山頂からのわずかな斜面はパウダースノー。これだけ日射しがあっても気温はマイナス8度だから、雪は湿らない。
三段山(1748m) 2022.1.21

三段山はベースとなる白銀荘とともに有名で、一度は訪ねてみたいと思っていた。下半分は樹林帯、上半分は森林限界を抜け出た斜面。楽しめるかどうかは天候と雪質による。
前夜は銀山荘に泊り、十分に支度して出発。森林限界を出てからは吹きっさらしで強風と低温に痛められた。頂上間近で女房のシールがはがれるなどアクシデントもあったが、山やの性か頂への執着は強く、そこを踏む。下山はコースミスをしないよう刻みながら滑ったが、傾斜も分からないような視界で、2度ほど立ちごけをした。視界のきくようになった下半は、気持ちの良いパウダーラン。楽しめる。
十勝岳(2077m)・美瑛岳(2052m) 2014.7.11
白金温泉を経て望岳台へ。数台の車が停まっていて、マイクロバスに乗ってガイドツアーの客も続々とやってくる。その列に組み込まれないように早々に山頂を目指した。この山は1988年に小噴火を繰り返し、入山禁止になるような活火山。今も噴煙を上げている。草木も少なく、行ったことはないけどまるで月面のような荒涼とした風景の中を歩くことになる。ところが、山頂から美瑛岳へと回っていくと、この月面はチングルマの花盛り。多くの登山者はここまで足を伸ばさないようだ。山頂でゆっくりと過ごすことができた。お花畑と下山後の温泉は、この山々のもてなしのように思える。
トムラウシ山(2141m) 2014.7.19~20
山は山頂を踏むだけでなく、どこからどう登るかということが重要。沢は山頂にいたる原初の道と言ってもよく、北海道の道なき山にはそのようなルートが多い。
道なき道の雰囲気を味わいたくてトムラウシ山へはクワンナイ川から入った。長い河原歩きの後の後、魚止め滝からの1㌔㍍は滝の瀬十三丁と名付けられたナメが切れ間なく続く。まさしく水のハイウェイである。源頭近くでキャンプをし、翌朝に日本庭園を歩いた。色とりどりのお花で埋められているが訪れる人も稀なようだ。北池を経てトムラウシ山頂を往復した。下山は化雲岳を経由して天人峡へと長い尾根道。下山後、天人峡温泉の湯につかると四肢がほぐれていくのにつれ、心の中に満ちてくるものを感じるのだった。
知床半島スキー縦断 三ツ峰(1509m)ルシャ山(848m)ポロモイ岳(992m)ウィーヌプリ(651m) 2012.4.30~5.4

4月28日~5月6日:北海道往復は新日本海フェリーで海の旅。飛行機より時間がかかるが、ゆったりとした時間がすごせる。
知床半島縦断は羅臼から足のそろった5名で出発した。ピークにはこだわらず、つながった雪を追うのがコースとなる。前半はテレマークスキーを駆使して快調だった。
2日目の泊地となったルサ川からの後半は雪が消え長い板を背にしての這松こぎとなり、枝を踏みながら空中戦。文字通りの無用の長物となったスキーは樺の木に引っかかる。時速200㍍のペース。知床岳へはいったん谷に下り、そこから雪のつながる尾根を登った。
ポロモイを過ぎ、ウィヌプリあたりからはやっと踏み跡らしいものが現れたが雨。ガスの向こうにヒグマがじっと我々を見ていた。最後に鹿よけフェンスを越えて知床岬の灯台へとたどりついた。岬の草原を抜けて文吉湾へ。
5日間で食糧はみんな食い尽くしひもじかった。おりしも北海道は記録的豪雨の大荒れ、その間隙をぬって野田船長のボートが迎えにきてくれ羅臼へ戻ることができた。2006年のシーカヤックによる知床半島一周に加え、今回もすばらしい旅ができた。ヒグマに会えたし、知床の大自然に惚れこんだ素敵な人たちにも出会えた。
帰宅後、ずっと履いていた像足をクリーニングに出したら、2重のビニール袋に入れられて「これは洗えません」と言って返されてきた。きっとみんな獣の臭いがしていたことだろう。
羅臼岳(1660m) 2006.8.16
羅臼岳は知床半島の根元にあり、知床峠からその美しい姿が眺められるのだが、我々が登った日は雨で視界なし。見えないヒグマを警戒しながらの登山となった。
北の岩尾別温泉にある木下小屋から登り、極楽平から大沢に入る。道脇には色とりどりの花が咲き、眺めのない道中を楽しませてくれる。三ツ峰と羅臼岳のコルは羅臼平と呼ばれ、幕営に適している。そこを南に折れ、ハイ松を出て岩場を登れば羅臼岳の山頂。雨と烈風で早々に退散した。
下山は羅臼へ。石清水から屏風岩への谷間を下る。泊場へ出て登山川を下れば硫黄臭く湯が湧いている所があるが、湯船はない。第二、第一の壁下の山腹を行き一息峠に出る。さらに谷あいを下れば、キャンパーでにぎわう熊の湯のキャンプ場に出た。
地西別川(羅臼湖) 2013.7.14
地西別川は羅臼湖を水源とする川で、距離はあるが初心者向でも遡行が楽しめる。
背丈よりも高いフキの林を抜けて、入渓する。水の中をざばざばと歩いて行く涼感がたまらない。難しい滝はないものの、スノーブリッジやハイ松漕ぎがあったりする。我々は1カ所、ルートを誤ってずいぶん時間をロスしてしまった。
そんなわけで、羅臼湖に出たときは陽が傾き、ヘッドランプを灯して湖の浅瀬を歩くことになった。半月が出て湖面を照らすのを美しいと思いながら知床峠へとつながる道をたどった。
斜里岳(1535m) 2013.7.17
登山口の清岳荘はしっかりした山小屋だ。そこから山腹の林道を行き、谷間の道に入ると沢歩きとなる。履物は沢靴のほうがいいかもしれない。羽衣の滝などもあって原初の山歩きとなる。でも、百迷山狂騒曲によるオーバーユースのおかげなのか、ストックの先にキャップをしろとか、携帯トイレを持てとか、規制はうるさい。稜線に出ると斜里岳は近い。たくさんの花々が咲き誇っていた。人気のわけは、これらの花か?それらを愛でながら頂上へ。
同じ道を帰る気がせず、竜神ノ池にも立ち寄ってみた。小さな池塘である。登りなおして尾根道を行き熊見峠から急な斜面の道をかけ下りた。
雌阿寒岳(1535m) 2014.7.11
雌阿寒岳は活火山である。麓の雌阿寒温泉を起点に山頂を経て、オンネトーへと周回するコースを選んだ。森林限界を抜けると、砂礫だらけの荒涼とした山腹が広がる。その色から青沼、赤沼と呼称される小さな池は、火口そのものであり、周囲からは噴煙も上がっている。その外輪を回って、阿寒富士とのコルに下りる。そこから下りついた先には、深い森の緑と、オンネトーの青い湖水が待っていてくれる。
社満射岳(1062m)・タケノコ山(1039m)
日勝峠(日勝ピーク:1445m・熊見山:1175m) 2022.1.24

日高と十勝を分ける日勝峠をはさんで北に熊見山、南に日勝ピークがある。峠自体の標高がすでに1106㍍だから、登る労力は少なく高高度の分だけ雪質はよい。こんな理由からバックカントリーの人気エリアになっているようだ。
私たちは日勝ピークの南にある沙流岳を訪ねる予定だったが、悪天にはばまれ日勝ピークで引き返した。ひと滑りしてから車を走らせ熊見山も登ってみた。いずれも2時間もあれば山頂を踏めるが、こんなたおやかな山で意味もなく急ぐのは野暮というものだ。日中になっても気温が低いので雪は軽く、北海道のパウダーを存分に楽しませてもらった。次は労山熊見山の開けたバーンを滑りたいものだ。
冬の山では霧氷やエビのシッポなど珍しくないけど、このサラサラの雪にはめったに会えるものではない。それにダイヤモンドダストも。でも、これも北海道の人にとっては当たり前、日常にあるものなんだろう。
オダッシュ山(1097m) 2022.1.23

新得町の西にそびえるオダッシュ山。除雪終点に車を置いて歩きだす。根室本線、道東自動車道の下をくぐり夏の登山口。
夏道は取らず、樹林帯のゆるい登りから急な山腹にジグを切って進み、夏道の通る尾根に出た。この山腹は開けていて帰路の楽しみに思えた。それに反して尾根は硬軟のシュカブラで滑りにくそう。前峰からオダッシュ山へと尾根を行き頂上に立つ。十勝平野や左幌岳の展望を楽しんでから、シールをつけたまま前峰まで戻る。
下山にかかったが、予想通り尾根筋はけっこう苦労させられた。尾根を離れてからは快適な滑降。登りのトレースを追いながら、あっという間に車へと戻った。
幌尻岳(2052m) 2014.7.21~22
Mさんと連絡が取れて、幌尻岳に登ることになった。この山に入るには幌尻山荘とバスの予約が必要だが、飛びこみで行くことができたのはラッキー。入山に関して条件の多い山は、なんとなく気が重い。戸蔦別のほうから入ってもよかったのだろうか。
第一ゲートから7.5㌔㍍の林道を歩いたのち、額平川沿いに徒渉を交えて幌尻山荘まで行って宿泊。翌朝は北沢を遡りカールへと出た。このコースは古いガイドブックには登山道(一般向けではない)として紹介されている。でも、今は踏み跡すらなく入る人も少ないようだ。おかげで人の臭いのしないカール底は別世界。ヒグマの大きな糞を踏んでしまった。久々に原初の頃の山の雰囲気、あの、わかる人にだけにしかわからない空気をだれが知ろう。
著作
海旅入門

日本の海をシーカヤックで旅するのに、
今ノトコロこれに優る入門書はないだろうと自負しています。
これから始める人も経験者も、ぜひ一度読んでみてください。
第1章はシーカヤックで海を旅するために必要なノウハウ
第2章は私のシーカヤックのフィールドと紀行になります。
途中に挿入されたエッセイもお楽しみください。
購入は書店または「舵社」からhttps://www.kazi.co.jp/public/book/bk11/1525.html 👈ここをクリック
山・岩・沢・雪(山蹊記2)