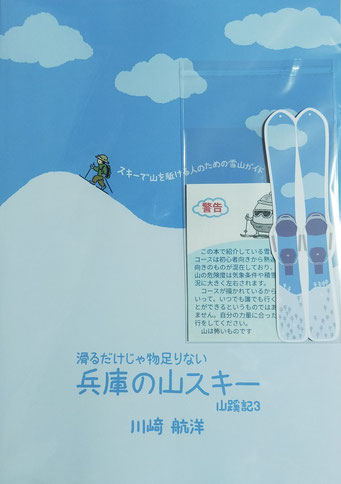恒例餅つき

12月30日:我家の歳末の餅つきは私が子供の頃から50年以上続いています。郷里の津山で、祖父母、両親、兄弟、近所の人で裸電灯の下で餅つきをしたことはセピア色の写真のような記憶としてはっきりと残っています。その祖父母、両親も今はなく、臼も杵も2代目になり、餅をつく場所も加古川、三木と移って、私たちもいつの間にか父母から祖父母という立場になってしまいました。この餅つきに子供たちが帰ってきてくれます。杵の音と笑い声につつまれた暖かな一日、こうしておだやかに世代が変わっていくこと以上の喜びはそう多くはないように思えるのです。
ストーブの日

12月18日:今日は朝から冷たい雨の降る日でした。スキーへ行く準備でスタッドレスタイヤに履き替えた後は、一日中家の中で過ごしました。薪が赤々と燃えて部屋は暖かく、本を読んでは寝る、起きてはお茶を飲む・・・の怠惰な時間。塩野七生の「海の都の物語」の一巻を読みおえて、続きを借りに行こうと思った時には、もう外は暗くなっていました。
薪割の日

12月10日:倒した木を割る手伝いに行きました。樫の根元は直径60㌢以上はあって女房の腰回りくらいか?なかなか手ごわい。何回か斧を振り下ろすとはじきかえされる音が変わって、次の瞬間に真っ二つに割れます。私ではパワー不足、これはもっぱらM君の仕事。半分になると私の出番で、ここからはパカンパカンと気持ちよく割れていってくれ、ストレス解消になります。それでも一日中やると腕も重くなり、右手の親指のつけ根に力が入らなくなっていました。帰りにたくさん薪をいただいたので薪ストーブの燃料もこれで一安心です。感謝。
雪彦山(地蔵の東稜)

12月3日:久々の雪彦でした。坂根の村はさびれた感じがし、少し寂しさを覚えました。岩場へのアプローチは新しい巻道がつけられ迷いそうでしたし、地蔵の東稜のやさしい岩場には無用なペツルがいっぱい打ち込まれ、なぜかチョークの跡までが?!頂上ファイス手前は倒木で荒れた感じに。等々、昔と思い比べながらも雪彦の乾いた岩の感触を十分に楽しめた一日でした。いい機会をあたえてくださったM・S・Iさん、ありがとうございました。登攀中の緊張感も夕暮れのせまる地蔵の頭でのくつろぎもいい時間でしたね。
石垣島:於茂登岳(526m)

11月15日~17日:波照間島から石垣島にもどり、レンタカーを借りて、北端の平久保崎から川平湾、観音崎まで島一周のドライブ。夜は「琉歌」という居酒屋で三線のライブを見て過ごしました。翌日はこの島の最高峰であり、沖縄県で一番高い山「於茂登岳」へ。1時間ほどで登れる山でしたが、内地と違う植生や頂上からのリーフに囲まれた島の眺望がとても印象的でした。下山してからたまたま開かれていた「第2回シネマフェスティバル」で映画を見たあと「てっぺん」という店で寿司を食べてこの日は終わり。翌日は、「比嘉」へ豆腐を2度も食べに行って店の人に笑われました。昼には、精肉店で石垣牛のサーロインを300g買い、真喜良の浜に行って焼いて食べました。夜はベストインにチェックインした後、2週間前にカヤックで出発した真栄里浜のはずれに出てお好み焼きをつくり、それを肴に打ち上げの乾杯。満月が明るく海を照らし、その月の側らを石垣空港に着陸する飛行機が光りながら下りていました。旅の終わりのいい夜でした。
西表島シーカヤック(8)

11月12・13日:雨 東風8~15m/sec 波高2.5~3m
11月から3月頃まで八重山の天候は良くなく、シーカヤックに向く季節ではないようです。昨日からの天気はまさにそうで、後半の行程を変更せざるを得ません。ザックを失くしたこともあって古見岳登山と西表島縦断は止め、新城島・黒島を経由して石垣島へ帰るプランも破棄しました。そんなわけで、12日はレンタカーを借りて島内観光、行きそびれた浦内川など訪ねてみました。13日は風雨をついて仲間川に入り、マングローブやサキシマスオウ、ヤエヤマヤシを見、展望台からの展望、川の終点地での食事など楽しみました。帰ってファルトをたたみ、前半のまずまずの天気に感謝しながら西表島1周の旅を閉じました。
西表島シーカヤック(7)

11月11日:雨 東の風8~12m/sec 波高3m
雨の音で目がさめました。昨夕になくした防水バッグに入れたザックを探しに浜を歩きましたが結局見つかりませんでした。ザックがなければ西表島縦断のトレッキングができなくなることが残念ですが、ない物はない。西表島のもうひとつの悲しい歴史を記した「忘勿石」を見てこの浜を出ました。強い風が真向いから吹いていて、南風見崎あたりでは気を抜くとすぐに岩礁へと押しやられるほどでした。それでも今日は漕ぐ距離も短く、気楽なものでした。連絡船の着く仲間港の右手にある漁船揚場に着けて終了。そこで偶然に通りかかったカヌーガイドのYさんに拾ってもらい、ヤマネコ荘という民宿に荷物ともども車で運んでいただきました。感謝。
西表島シーカヤック(6)

11月10日:晴時々曇 東の風3~6m/sec 波高2~3m
この日はバイミ崎を回って南風見田の浜まで30Km強を漕ぐことになります。ふなうき荘の主人に2009年10月にシーカヤックの遭難があって1人行方不明のままとか、宿の客で2度出かけたが2度ともバイミ崎を回れず帰ってきたとか、途中の廃村跡には不審者が住みついているから気をつけろとか、さんざん脅かされていたので内心不安でした。船浮を出てサバ崎、崎山湾を横切るまでは快調で、ダイビングの船も来ているぐらいだから天気もくずれないだろう、このまま行けば昼過ぎにはなどと思っていたのですが。
「岬は荒れる」のセオリーどおり少し荒い波の立つバイミ崎をまわりました。問題はこの後でした。とんと舟が進まなくなり、漕いでも景色がなかなか変わらなくなったのです。前方にかすんで見えるウビラ石の突端も近づきません。初めは「海坊主につかまった」などと冗談を言っていたのですが、いくら漕いでも越されないウビラ石あたりでは眉が吊り上っていました。漕ぎ続けであまりにしんどいので、手を止めるとたちまち逆戻りし、その距離を取り返すのに30分かかるという有様。間近に見えるベーブ石まで1時間半、落水崎までさらに1時間半かかり、バイミ崎からここまでのわずか4Kmほどに5時間かかっていました。どこか浜に上げて休みたかったのですが、海岸線は白波が砕けていてそれも許されません。この岬を回ることの難しさと危うさはこんなところにもあります。結局、この日は鹿川湾口を横切りに南風見田浜まで漕ぐしかありませんでした。最後に暗くなりかけたリーフで横波を3回受け、沈ははしなかったものの、デッキに積んでいたザックを持っていかれてしまいました。浜に上がって、からからの喉に水を流し込み、ふなうき荘の奥さんがにぎってくれたおにぎりをペコペコの腹にためると、正体もなく眠り込んでしまいました。長い旅にはこんな日もあるようです
西表島シーカヤック(5)

11月9日:晴 南東の風 風速6~10m/sec 晴時々曇
祖納から右手に離島(パナリ島)を見ながら逆風をついて漕ぎ進んだ後、白浜に上がって町内見物。港の待合室のパネルを見て、離島にはかつて炭鉱があって楽園に思える西表にも暗い歴史の一面があることを知りました。マングローブの景観を楽しみながら仲良川を遡ると、いつしか汽水域を過ぎ、ヒルギにかわってアダンの木を見るようになります。カヤックの終点から歩いてナーラの滝まで行き昼食。帰りは船浮湾を横切って落水の滝へ行きたかったのですが、アゲインストの風が強く、あきらめました。方向を変えるとその風に押されてたちまち船浮の港へ。ここは船でしか来ることができない村で、ふなうき荘に泊まりました。この宿でのひと時は色々あって愉快でした。旅ではどんな人に会うかが大事なようです。
西表島シーカヤック(4)

11月8日:雨後晴、東の風8m後1~2m/sec、波高2m後1m
天気予報は曇後晴でしたが、朝から間欠的に強い雨が降り、海に出る気になれませんでした。横浜から来たという同宿の人と話をしながら回復を待っていましたが、11時頃になって少し晴れ間も見えてきたので出発しました。しばらくは風雨にもてあそばれましたが、星砂の浜に着く頃は海もおだやかになり、宇奈利崎の狭いリーフ帯も難なく回りこんで浦内湾へ。さらに漕いで名も知らない浜にあげスノーケリングを楽しみました。クマノミやカラフルな熱帯魚の歓迎に気をよくして泡盛で酒宴。二人で1本を空けてしまったのは、とても気分がよかったから。へらへら漕いで祖納の北浜で終了、宿は星砂荘。夜に夜光虫を見に沖へと漕いでみました。
西表島シーカヤック(3)

11月7日:曇・東後北東の風・8~10m/sec・波高2~3m
朝起きてみておどろきました。昨日寄せた浜の沖合はるか彼方まで干上がっているのです。これではとても舟は出せません。仕方なく潮が満ちてくるまで待ち、8時前ようやく水際まで舟を運び漕ぎだしましたが、底すりに神経を使います。おまけに向かい風。野原崎を回るとやっと横風に変わってくれたので助かりましたが、リーフの縁は大きな白波が立っています。強風で飛ぶしぶきに右半身を濡らしながら漕ぎ進み、途中でユツン川に入りこみマングローブを、ピナイ川では滝を見物しました。河口は干潟になっているので深間を探して行かなければ下りて舟を引くことになります。西表の北の玄関、上原港に上げカンピラ荘を宿としました。
西表島シーカヤック(2)

11月6日:曇時々晴、東の風、風速5~8m/sec、波高1.5~2m。
支度に手間どって、出発は8時過ぎになりました。真栄里ビーチから石垣港を回りこみましたが、この間が思いのほか長く、観音崎あたりから出れば半分の航程ですんだと後から気がつきました。石垣、西表間のリーフは美しく、見たことのない透きとおった青い海の上を漕ぎます。竹富島に上がり自転車を借り、一般客にまじって島一周の観光。再び小浜島を目指して漕ぎだすと、右手に薄い砂浜が見えました。陽が当たるとはっきりと輝き、陽が陰ると消えてしまう蜃気楼のような浜でした。遠回りになりますが、これに魅かれて漕ぎ、ついに着きました。干潮時にだけ現れる幻の島のようで、この体験さえ幻ではないかと思うほど美しい浜でした。その後、小浜島へと進み、この島の最高峰「大岳」に登りました。さらにヨナラ水道をわたって西表島の浜にあげたときはもう夕刻になっていました。
西表島シーカヤック(1)

11月5日:テントレックの今年最後の旅は西表島です。神戸から直行のスカイマークが出ており、昼前には石垣島に着きました。旅の目的には土地の物を食べることがあります。早速、空港の食堂でソーキソバと海ブドウを食べ、それからレンタカーを借りて友人のKさんに紹介していただいたパイナップルの生産農家へおじゃましました。ちょうど来客中でしたが、いっしょにマンゴージュースやパイナップルをいただき大満足。ソバも勧めてくださったのですが、もう腹いっぱいで空港で食べてきたことを悔やみました。その後、買い出しをしてから真栄里ビーチの近くのベストインに泊り、翌朝の出発の準備を整えました。
枚方ポタリング

10月30日:北河内自転車道を使っての久々のポタリング。師匠のmaruchanと自転車デビューのYさんと女房の4人で淀川沿いに北上、枚方宿を通りぬけて関西外語大学の学食「アマーク・ド・パラディICC」でワンコインの昼食をとったあと、今日の目的のステンドグラス工房「GlassWorksあまね」へ行きました。ここは私のカヤックの師匠の娘さんがやっていて、ステンドグラスの作り方を教えてもらいました。写真が私たちの作品です。夢中で作っているとまたたく間に時間が過ぎて、夕やみせまる淀川河川敷を帰ることに・・・。(つづく)
高島トレイル(秋)

10月14~16日:高島トレイルの最終行程は水坂峠から三国岳までの約40㌔㍍です。下山予定地の桑原に車を置き、薮山雲水さんに送っていただいて水坂峠へ。雲水さんとは二の谷山で別れ、南下していきました。初日は横谷峠でキャンプ。台風26号が来ているのは織り込みずみでツェルトでなくテント持参です。案の定、翌日は昼過ぎから雨模様、おにゅう峠で下山しようか迷いましたが、ラジオの予報では台風の進路は関東方面、直撃ではないので歩を進めました。ナベクボ峠の手前で風を避けて2日目の夜。深夜から未明にかけて風雨が強まったものの、木立に守られて飛ばされるほどではありません。明けて翌日、高島トレイルの最後は、雨にぬれ風にあおられての山歩き。こんなフィナーレもあるのでしょう。
カヌーワールド

10月12日:カヌーワールド7号に2回目のコラムを載せていただきました。83ページでタイトルは「海と女房と二人艇」です。カヌーワールドは春秋2回の発行、今回は全国のカヌーイベントの特集があります。また、最新の装備や技術等の情報満載なのでお薦め。定価もこの内容・ボリュームで千円は安いと思います。立ち読みでなく、ぜひお買い求めを。
大阪ポタリング

9月30日:大阪に用事があって、ついでにポタリングしてきました。娘婿の車に便乗、茨木で下してもらい北大阪サイクルラインへ。暑いくらいの陽ざしでも、自転車で走ると風がさわやかでした。鳥飼大橋をわたって、淀川沿いにくだるとキタの摩天楼が間近になり、伊丹へ着陸する飛行機が轟音を残して頭上を降下していきます。市街へ入ると天神橋筋。ちょうどお昼になっていたので、食いもん屋を探してうろうろするのも楽しいものでした。
高御位山

9月17日:台風後の快晴。朝の涼しさに誘われて高御位山に歩きに行ってきました。競馬街道から登る「北コース」へ入り、松の木谷池の東岸を経て尾根にとりつきます。急登のあとにわずかな岩尾根が出てきたのが唯一気持ちのよい場所で、あとはヤブのうるさい道を登ります。高御位の西の肩といっていい尾根に出ましたが、頂上へは寄らずそのまま縦走路を西進、市ノ池への分岐を見送った先で北に分け入る踏み跡を下山路としました。北コースよりこちらの方が歩きやすかったのですが、最後に落とし穴。松の木谷池の水位が高く道が水没していて、徒渉とヤブ漕ぎを強いられました。山は最後まで何があるかわかりませんね。
高御位山(299.8m)

9月9日:長雨つづきの後の久しぶりの青空。少し暑かったのですが歩きに行ってきました。yo4o3さんにいただいた地図をたよりに、高御位山の北面の山道に入ってみました。実はこんな所に道があることを知らなかったので、気になって仕方なかったのです。奥池から隠れ谷を登って頂上、下山は千込め谷か桜谷かを下りたのでしょうがよくわかりません。帰りの駄賃にタヌキ岩の道もたどってみたものの、草深で女房の文句を聞くはめになってしまいました。平日でもたくさんの人が登ってきていて、知り合いのOさん夫妻にもお会いしました。10年ぶりくらいの高御位山、懐かしさと新鮮さが入り混じった不思議な気持ちでした。
隠岐島シーカヤック

8月22~23日:隠岐島は2度目です。同じ場所を訪ねることはあまりない私ですが、ここと知床は別で、みっちゃんのリクエストのおかげで再訪できました。Mさんに女房が加わり4人、フジタの2人艇2艇で行きました。西の島の別府港から町営バスで三度まで。そこからスタートし矢走26穴、明暗の岩屋、屏風岩を見て国賀海岸にあげました。標高257㍍の魔天涯を往復するトレッキングをしてから、再び舟に。通天門、乙姫御殿を巡り、魔天涯の絶壁を見上げて漕ぐうちに夕陽が雲間に少し顔をのぞかせて沈んでいきました。外浜に泊まった翌日は、東国賀海岸をまわって耳々浦へ。最後は雷と驟雨にみまわれましたが、隠岐のハイライト部分を行く2日間は、中身の濃い印象深い海旅になりました。
屈斜路湖

7月18日:屈斜路湖の湖畔にある「和琴」「コタン」「池ノ湯」「砂湯」の温泉をカヤックでめぐってみました。いずれも無料、混浴(水着オーケー)です。最初は女房・みっちゃんのペアでしたが、温泉に着くごとに一人ずつ入れかわっていき、残る一人は車を回送します。和琴の共同浴場は熱すぎてかけ湯だけ。次のコタン温泉は湖畔の眺めもよく掃除もされていてよかったです。池ノ湯は施設が閉鎖されているのでしょうか手入れされてなく足湯だけにしました。最後の砂湯は砂浜を掘って入るのが面倒くさくてやめました。湖畔にテーブルと椅子を出して食べるカップ麺は、ロケーションのおかげで美味しいものになりました。
知西別川

7月14日:知西別川は羅臼湖を水源にもつ川で、この川を遡りました。記録では4~6時間だったので、6人という大人数でも8時間もみておけば十分だろうと思っていたのですが・・・。遡りはじめてすぐにここが「谷」でなく「川」と呼ばれているかに気づきました。登っても登っても水量が減らないのです。たいした滝もないのですが、水と巨岩にはばまれ雪渓に迷い、ハイ松を漕ぎ、羅臼湖畔にたどりついたのは夜の8時。三日月が湖面に浮かんでいました。湖の浅瀬を歩いて遊歩道へ、さらに1時間ほど散策路をたどって車道へ出たのは10時でした。心配して迎えに来てくれた桜井ガイドの「これも記録だよ」の言葉が皮肉ではなく、温かく感じられたのです。
乗鞍スキー横断

3月25~27日:3年前の2月に敗退した飛騨高山スキー場から乗鞍高原への横断コースを、今回は逆から攻めました。同行はS店長と前回のパートナーM君で、強力メンバーです。初日は剣ヶ峰をこえて奥千町ヶ原避難小屋まで、カリカリにクラストした斜面の登下降。翌日は夜半にふったアスピリンのような雪をすべり、心配した丸黒山の登りも難なくこなして枯松平の休憩所へ入りました。快晴のこの日に全行程を終えることもできたのですが、休憩所でゆっくりと山の時間をすごすことにしました。3日目は早朝に出発し、飛騨高山スキー場までピックアップにきてくださるKさんを待ちながらゲレンデ滑降をたのしみました。(フォトレポート参照)
セツドウくん

2月13日:テレマーク用のアイゼン「アイゼくん」を作った一新工業さんの次の雪山用具はスノースコップ「セツドウくん」。掘る、削る、運ぶの機能にスノーソーの切るを加えた逸品。シャフトは伸縮、ブレードとは別収納。そのブレードはオスプレイの28㍑ザックの背におさまる大きさ、重さも590gと軽量。雪洞掘りでしばしば出くわす氷の層、それを切り崩すのにいちいちスノーソーに持ちかえなくてもワリワリと掘っていけます。この日1時間余で2人用の雪洞を完成させました。これはいけるかも。
私の書いた本
海旅入門

日本の海をシーカヤックで旅するのに、
今ノトコロこれに優る入門書はないだろうと自負しています。
これから始める人も経験者も、ぜひ一度読んでみてください。
第1章はシーカヤックで海を旅するために必要なノウハウ
第2章は私のシーカヤックのフィールドと紀行になります。
途中に挿入されたエッセイもお楽しみください。
購入は書店または「舵社」からhttps://www.kazi.co.jp/public/book/bk11/1525.html 👈ここをクリック
山・岩・沢・雪(山蹊記2)